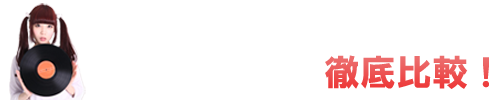その前衛性や退廃的な雰囲気がポップ・アートの巨匠アンディ・ウォーホルを魅了し、彼の力でアンダーグラウンド芸術という視点から紹介されデビューしたヴェルヴェット・アンダーグラウンド。そのリーダーとして60年代ロック・シーンに登場したのが、ルー・リードでした。ヴェルヴェッツ解散後も退廃かつ倒錯的な楽曲の発表、グラム・ロックやパンク・ロックとしての高い評価、インストによる前衛アルバムの制作、そしてボブ・ディランに並ぶロックの詩人としての高い評価など、その活動は常に挑戦的なものでした。
今回はルー・リードの名盤や高額買取りレコードを紹介させていただきます。
■Transformer (RCA, 1972)
本人には自分の長所は見えにくいもので、得意よりもやりたい事を優先しがちです。ヴェルヴェッツの研究書『Up-Tight: The Velvet Underground Story』によると、ヴェルヴェッツ結成前のルー・リードはチャート音楽の作曲をして小遣いを稼いでいたそうですが、それぐらいに元々ソングライターやシンプルなロックンロールの志向が強かったようです。初期ヴェルヴェッツのような前衛性や退廃芸術的な指向はそこまで強くなかったのではないでしょうか。実際のところ、音楽大学で現代音楽を学んでいたジョン・ケイルがヴェルヴェット・アンダーグラウンドを去ると、ヴェルヴェッツから前衛性はなくなり、フォークやシンプルなロックンロールが多くを占めるようになりました。それは、ルー・リードがソロになってからも続きます。
しかし、初期ヴェルヴェッツが持つ退廃的な観念こそルー・リードが持つ独自性と見抜いた人物がいました。デヴィッド・ボウイです。ボウイ自身のレコードを見る限り、デヴィッド・ボウイは長所を見抜き、それを伝わりやすくなるようプロダクション/ディレクションする際に長けた人物のようです。ボウイは懐刀であったミック・ロンソンを携え、評価は高かったもののセールスに結びつかなかったルーのアルバム制作を行う事になりました。それがこのセカンド・アルバム『トランスフォーマー』です。
ボウイがルーのどこに注目したのかは、アルバム冒頭に「Vicious(背徳)」を持ってくる点などにも現れていますが、このアルバムの色を決めた決定打は「Walk on the Wild Side」ではないでしょうか。コーラスごとに現代アメリカの闇を生きる人々を訥々と歌った、アメリカ現代詩のような歌詞を持つ曲です。
1小節おきにトニックとサブドミナントを行き来する平歌部分、これを詩の内容に即してより浮遊感を出すため、長7度から始まるカウンターラインを作り、それを執拗に繰り返したことが、ルー・リード初のシングル・チャート入りを果たした最大の要因だったのではないかと思います。この芸当がボウイに出来たとは思えないので、恐らくミック・ロンソンのアイデアだったのでしょうが、こういう事を出来る人物を引っ張ってくるのもまたプロデュース能力のひとつでしょう。

■Berlin (RCA, 1973)
ルー・リードはいくつかの際立った才能と、ミュージシャンとして致命傷となる弱点が同居している人物と感じます。才能部分を言えば、大戦後にひとり勝ちとなったアメリカの闇を捉え言語化した、その鋭い観察眼と言語センスです。さらに、ヴェルヴェッツ以前から認められていたリート作曲の才能もあります。それらを自覚したのが『トランスフォーマー』だったのでしょうが、その長所をさらに洗練させ、完成度を高めたのが『ベルリン』だったのではないでしょうか。
アラン・マクミランによるピアノ伴奏のみで歌われる退廃感あふれる「ベルリン」から始まる本作は、ある男と娼婦の物語です。娼婦キャロラインは最後に…。
発売当初、ローリング・ストーンズ誌は本作を酷評したそうですが、もし私がルー・リードのソロ・アルバムから1枚だけ選ぶとしたら、間違いなくこのアルバム。『トランスフォーマー』をはるかに凌ぐ、ロック史に残る大名盤と思います。
■Metal Machine Music (RCA, 1975)
ロックンロールへの傾斜。フォーク・リヴァイバルから連綿と続くフォーク・ミュージックの正当な継承者。アメリカ現代詩に通じる社会派詩人としての視点…ルー・リードは様々な面を持つアーティストですが、もうひとつ忘れてはいけないのが、彼を音楽シーンに押し上げる最大の武器となった前衛芸術/モダン・アート的な側面ではないでしょうか。ヴォーカルなし、トレモロやモジュレーターで加工された電子音が飛び交うノイズ・ミュージックと呼ばれ物議をかもしたのが本作です。
ノイズと言ってもホワイトノイズは鳴っておらず、分離した音源はそれぞれに相関性を持ち、またその音は耳障りどころか心地よいほどです。その中に冗長を避けるようにオブリガートとしての電子変調が割込みます。つまり、既存の音楽スタイルを取っていないだけで、相当に構成された音楽です。
ルー・リードのキャリアだけで判断すると理解しにくいかも知れませが、フルクサスやフィリップ・グラス、ローリー・アンダーソン、そしてアンディ・ウォーホルが制作した実験映画といったアメリカン・モダン・アートという視点からこのアルバムを聴くと、その理解ははやいかも知れません。しかも、よく出来た作品と感じるのではないかと思います。
■New York (Sire, 1989)
ルー・リードはポップでもあり挑戦的なアーティストでもあるという、相反する個性を持っていると感じますが、こういう姿勢は裏目に出ると支離滅裂になるのかも知れません。70年代後半からのルーは、そうした意味で迷走したように見えますが、そんなルー・リードが、ついに自分のやってきたことをまとめ上げたように見えたのが、89年『ニューヨーク』と、なんとヴェルヴェッツ以来のジョン・ケイルとの共演となった90年『ソングス・フォー・ドレラ』でした。
『ニューヨーク』は一聴するとシンプルなロックンロールに聴こえるアルバムですが、ボブ・ディランやラップに匹敵する、歌とポエトリー・リーディングの中間を縫う独特の歌唱は、曲と一体になってここで完成の域に達しています。ジャズやロックのジャムにも聴こえるルーズな曲と演奏は、この詩と歌唱のスタイルに対応したものでしょう。そして、すべての曲がまるで短編小説のような素晴らしい詩で出来ていて…アメリカ現代詩の延長に位置する、ロックの外套を纏った素晴らしいフォーク・ミュージックと思います。
■レコード高価買取に関するあれこれ
人気の高い『トランスフォーマー』はレコードであるだけで高額必至。国内帯つきは5000円越え、72年プレスではUK盤もUS盤も高額で、1万円越えとなる事もあります。
『ベルリン』は、国内盤は今でも手軽な価格で入手できますが、帯つき美品となると値が上がるようです。一方、US盤UK盤の73年オリジナルはさすがのプレミアになっています。
『メタル・マシーン・ミュージック』は希少価値と人気が相反するのか、US盤も日本盤も1万円に迫る時もあれば、意外と安価で取引される事もあります。このアルバムには、ルー・リードのアップがジャケットとなっているThe Amine β Ring 盤というのがあり、これは収録時間などに差がありますが、この評価が意外に高いです。しかし入手は少し難しいかも知れません。
『New York』はCD時代になってからの発表のため、LPがレア、高額化しています。しかしこの作品は詩が素晴らしいため、英語が苦手な人は、ぜひ訳詩の載った日本盤CDを手にしてほしいです。ルー・リードの作品は日本盤でも訳詩が載っていない事がありますが、少なくとも本作の日本盤初期のものは訳詩が掲載されていました。
もし、ルー・リードのレコードを譲ろうと思っていらっしゃる方がいましたら、その価値が分かる専門の買い取り業者に査定を依頼してみてはいかがでしょうか。